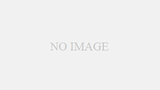研究活動のページに今年度の卒論・修論の要旨を掲載しました。
昨年からゼミの活動フィールドに児童発達支援事業所が加わったので,卒論研究では発達支援の分野で活かせる課題の開発や評価を行いました。現場で使える課題の研究はおもしろいです。
修論研究の「地域包括ケアシステムの中で心理学に何ができるか?」は中国四国心理学会で学会賞を受賞しました。2018年度,2021年度の日本心理学会,2022年度の中国四国心理学会の受賞に続いてゼミの卒論・修論では4度目の受賞になります。うちのゼミ研究,それなりにがんばっていると思う。
卒業論文
発達障害児の認知機能評価・訓練プログラムの開発(1)―児童発達支援事業所における有効性の評価―
認知機能評価や訓練に使う目的でゼミで開発してきた「もぐらたたきゲーム」を,3~18歳の定型発達児者と3~5歳の発達障害児に遊んでもらって,その結果を分析しました。画面に出てくる動物を全部叩けばいい「ディストラクタなし」条件,簡単に見分けられる爆弾を避けて叩く「爆弾ディストラクタ」条件,見分けが難しいねずみを避けて叩く「動物ディストラクタ」条件の3つの条件下でゲームを行ったところ,まず定型発達児において,動物ディストラクタは年齢にかかわらずゲームを難しくしたのに対し,爆弾ディストラクタは低年齢の子どもの場合に特にゲーム成績に影響することがわかりました。同じ課題を発達障害児にやってもらったところ,同年齢の定型発達児よりもさらに爆弾ディストラクタに影響されることがわかりました。このことから,発達障害児は容易に識別できる対象も無視できない特徴をもつことがわかりました。この研究結果は,発達障害児に対するビジョントレーニングの必要性を支持するエビデンスのひとつと考えています。

発達障害児の認知機能評価・訓練プログラムの開発(2)―児童発達支援向けの新たなプログラムの提案―
脳の前頭葉に損傷を受けると,日常生活において目標を設定してそれを計画的・効果的に遂行できない「遂行機能障害」と呼ばれる障害があらわれます。脳障害がなくても,遂行機能に問題があると,「集中できない」,「やる気がおきない」,「うっかりミスや物忘れが多い」,「何ごとも中途半端になってしまう」,「くよくよ考えて行動できない」,「仕事がたくさんあると手に負えなくなる」,「先が見通せず希望がもてない」,「ついキレてしまう」などの症状がでます。これらは一般人の日常にも見られる「あるある」症状ではないでしょうか。本研究では,「ウィスコンシンカード分類課題」(WCST)という神経心理学的検査にヒントを得て,次元カードマッチング課題(dimensional card matching task, DCMT)を開発しました。これは,色・形・数の3つの属性のうちのいずれかでマッチする2枚のカードを選ぶと正解となるので,そのルールを探していくゲームです。正解のルールはゲーム中に変化するので,プレイヤーはそれに適応しながら正解を探していかなければなりません。DCMTは知覚的にカードを照合するだけでなく,神経衰弱ゲームとして行うことで(記憶モード),ワーキングメモリに負荷をかけた状態で対象者の反応を調べることもできるようになっています。WCSTとDCMTのそれぞれの結果を,神経心理学的検査「遂行機能障害症候群の行動評価(BADS)」に含まれる遂行機能障害質問紙(DEX)のスコアとの相関分析にかけたところ,WCSTの達成カテゴリー数(CA)とDEXの相関が.455(絶対値)で最大相関値であったのに対し,私たちの課題は知覚モードで.612,記憶モードで.540と,より高い相関値を示しました。偶然の一致に左右される誤差を多く含む記憶モードでも高い相関が得られたことから,DCMTの結果を詳細に解析することで,前頭葉機能を測定・評価できる課題(さらには遊びを通して訓練できる課題)として使えるのではないかと我々は期待しています。

修士論文
ASD傾向,HSP傾向,抑うつ傾向と感覚特異性の関連について
近年,感覚感受性が強く,さまざまな刺激に敏感に反応することから,ストレスや生きづらさを感じやすい繊細な人々としてHSP(高敏感者)が知られるようになってきました。HSPはASD(自閉スペクトラム症)とは異なりますが,ASDも特異な感覚特性をもつことが知られています。また,両者とも,抑うつとの関連が指摘されています。そこで本研究では,ASD傾向,HSP傾向,抑うつ傾向,感覚特異性が相互にどのような関連にあるかを検討しました。調査の結果,HSP傾向とASD傾向には弱い正の相関がありました。また,感覚過敏と低登録(感覚鈍麻),感覚過敏と感覚回避,感覚回避と低登録の間にも有意な正の相関がみられました。さらに,このような特異な感覚特性は,HSP傾向,ASD傾向,抑うつ性とも関連することがわかりました。クラスター分析の結果,参加者は4群に分けられ,そのうち2つの群はASD傾向が高く,ASDの特徴である感覚過敏と感覚鈍麻が共存する特徴がみられました。また,そのうちの1群はHSP傾向も高く,その群のみ,突出して抑うつ傾向が高いことがわかりました。この研究は,①感覚過敏と感覚鈍麻のような相異なる感覚特性が共存しうるものであり,②それらを併せもつ者はASD傾向が高いのが特徴で,③さらにASD傾向とHSP傾向を併せもつ者は高い抑うつ性を示すことを明らかにした点に意義があると考えています。
地域包括ケアシステムの中で心理学に何ができるか?―認知機能トレーニングを用いたアクションリサーチ―
高齢化社会の進展に伴い,地域における認知症予防のための脳機能トレーニングのニーズが増しています。本研究では,単純な繰り返しによる長期記憶形成訓練を行うことで,ワーキングメモリの主要機能のひとつである短期記憶容量の増加が期待される訓練プログラムを,地域に暮らす高齢者を対象に実施し,大学生参加者の結果と比較しました。実験の結果,大学生においては,4週間の訓練によって長期記憶形成能力の指標である拡張数唱範囲は19.7桁から29.9桁へと1.5倍に拡大し,短期記憶容量の指標である数唱範囲も順唱課題で7.0桁から7.5桁,逆唱課題で6.2桁から6.7桁と統計的に有意に増加したのに対し,高齢者の拡張数唱範囲は9.8桁から9.3桁と,記憶範囲も少なく,訓練効果も認められませんでした。また,短期記憶容量への訓練効果の汎化も生じませんでした。高齢者の脳機能トレーニングの試みとしては失敗したものの,本研究は,高齢者が単純繰り返しによる長期記憶形成においても重度な記憶形成の困難をもつという科学的証拠を見出した点で,重要な発見をもたらしたと考えます。
抑うつ傾向が虚記憶に及ぼす影響
人は,実際に経験していないにもかかわらず,あたかも経験したかのように誤った情報を記憶として保持してしまうことがあり,これを「虚記憶」といいます。抑うつ状態では,ネガティブな感情や思考にとらわれ,ポジティブに物事を受け止めることが難しくなることから,本研究では,抑うつ傾向の強い者ほど,ネガティブな感情を想起しやすい状況において,虚記憶が形成されやすい傾向があるのではないかという仮説をもとに,抑うつ傾向と虚記憶形成の関連を検討しました。実験では,感情的に中立的なニュートラル語(たとえば「建物」)を想起させる刺激語と,負の感情を想起させるネガティブ語(たとえば「自殺」)を想起させる刺激語を用い,虚記憶形成パラダイムを用いて虚記憶の形成の度合いを測定し,参加者の抑うつ傾向との関連を調べました。その結果,抑うつが高いほどネガティブ語に対する虚記憶が形成されやすい傾向は認められませんでしたが,抑うつが高い者は,虚記憶で一般的にみられるターゲット語を「まちがいなく見た」と判断する傾向が有意に低いことが示されました。抑うつ者は,自分のことを他者より優れていると錯覚する一般的傾向がみられない「現実主義者」であると言われますが,本研究の結果は,記憶形成においても,抑うつ者は同様な「騙されない」性質をもつことを示した点で,興味深いものと考えています。